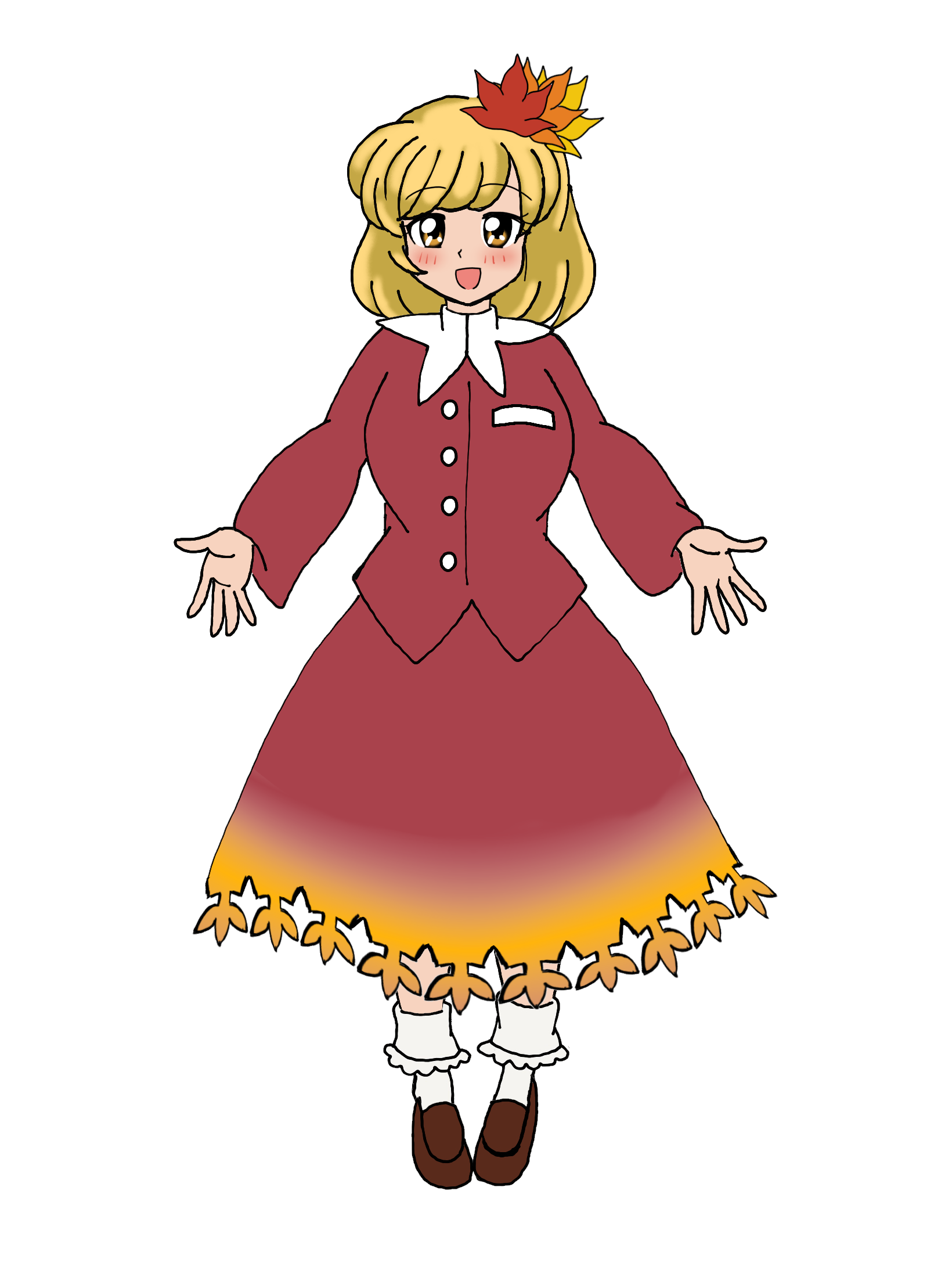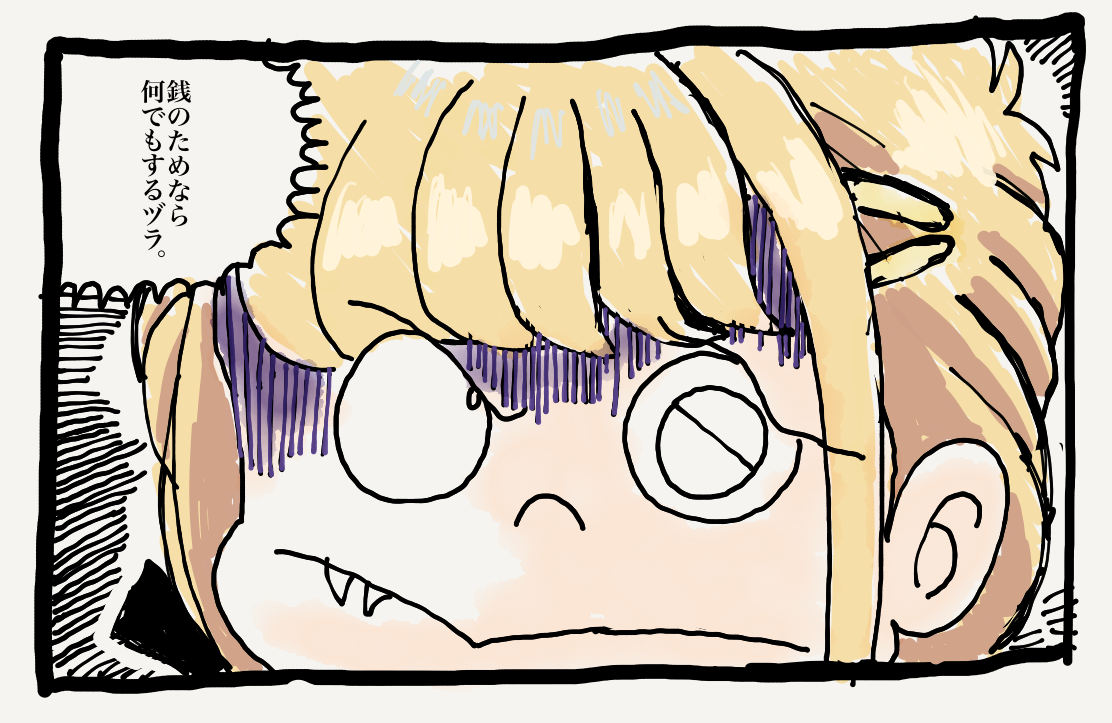No.110
○木野まこと オナニー 下半身のみ
#小説
前回の小説とは違うパターンです。
下半身のみのオナニーの小説です。
ある日、木野まことは街を歩いていた。彼女はいつものようにセーラー戦士として悪を追いかけていたが、今日は何かが違っていた。
木野まことは自室に戻り、悪の存在を感じながらも、落ち着こうと試みた。しかし、心がざわつき、体が火照ってしまった。
そんな時、彼女は机の引き出しから小さな玩具を見つけた。彼女は恥ずかしさを感じつつも、先ほどの男性を思い出し、手に取った。
木野まことは、自分の部屋でベッドの上に寝そべり、先輩にそっくりな男性を想像しながら、彼との濃厚なエッチな妄想を膨らませていた。
彼女は恥ずかしいけれど、どうしても満たされたい気持ちが抑えきれず、自分の股間を玩具で刺激しながら、先輩似の男性が自分の体に触れる様子を思い浮かべた。
「ああ、先輩…もう我慢できないよ…もっと私を抱いて欲しいの…」
木野まことは、先輩にそっくりな男性に執拗に責められる想像をして、自分のパンツを脱ぎ捨て、恥ずかしい部分を露わにした。そして、彼女はスカートをたくし上げ、挿入しやすい体勢に身を置いた。
「ああん、気持ちいいよぉ…先輩の感じ方が分かる気がする…!」
彼女は激しい動きで玩具を挿入し、自分の股間を抉り取るような快感に酔いしれた。先輩似の男性に抱かれ、彼女は何度も高まり、喘ぎ声を漏らしながら絶頂を迎えた。
「ああ、もう…先輩…もう少しで…あああっ!」
彼女は身体を震わせ、息を荒くしながら、自分自身を満足させた。
「先輩、今度会ったら、こんなにエッチなことされたらどうしよう…。でも、やっぱり…してほしい…」
木野まことは、彼女が自分自身に欲望を抱いていることに少し戸惑いながらも、この興奮を忘れることができず、再びエッチな妄想に耽り始めた。
深く突き刺さる快感に、まことは自分でも驚くような悲鳴を上げた。先輩そっくりの男性の陰茎が、自分の中で激しく動いている。その上から、別の手がクリトリスを弄りながら、まことを更に高みに誘っていた。
「あああっ、もうイッちゃう…イクイクイクっ!」
まことは必死で声を押し殺したが、とうとう自分の身体を抑えることができず、甘美な絶頂が押し寄せた。全身が痙攣し、目の前が一瞬白くなった。
その後、まことは呆然と横たわっていた。こんなに激しい快感を味わったのは初めてだった。先輩そっくりの男性に身体を貪られ、何度も何度も絶頂を迎えた。気がつけば、彼女はもう深夜で、明日は学校があるというのに、眠りに落ちてしまっていた。
翌日、まことは学校に行くのが億劫だった。一晩中、先輩そっくりの男性と快楽に没頭してしまったからだ。しかし、彼女が教室に入ると、そこには驚きの光景が広がっていた。
「木野さん、良かった。ちょうど君に言いたいことがあったんだ」
先生がまことに近づいてきた。クラスメイトたちが謎のワクワクした気配で彼女を見ている。
「え、どうかしましたか?」
「君が帰った後、校門前に先輩が来たんだよ。待ってるって。何か伝えたかったらしい。ちょっと急いでくれと。何だったんだろうね」
「あ、あの……ありがとうございます」
まことは、心臓が止まるかと思うほど興奮していた。こんな嬉しいことがあるだろうか。先輩が自分を待っている。早速、まことは教室を出て、校門前に向かった。
校門前で、まことは先輩そっくりの男性と出会った。彼はまことに優しく微笑みかけた。
「あ、先輩。お呼びですか?」
「ああ、まこと君。実は
まことは、先輩そっくりの玩具を使って、激しく自分を責め立てた。挿入された玩具が彼女の中で激しく動き、膣内を突き上げるように蠢いていた。
「ああっ、先輩、こんなに激しくされたら、私、もうダメぇ…」
まことは、先輩にそっくりの玩具を膣内に突き立てたまま、恥ずかしい喘ぎ声を漏らし、身体を震わせた。彼女は、自分で操作する玩具に慣れていたため、自分自身で快感をコントロールしながら、一人Hに耽っていた。
しかし、やがてまことは、もう少し激しい刺激を求め始めた。彼女は、自分で腰を動かしながら、玩具を膣内に押し込んだり引き抜いたりして、さらに快感を高めようとした。
「もうダメ、もう我慢できないっ!」
まことは、自分で腰を振りながら、熱くなった股間に激しい快感を感じ始めた。彼女は、先輩そっくりの玩具を激しく突き上げながら、自分で乱暴に責め立て、身体を震わせた。
「先輩、私、先輩が欲しいのっ!」
まことは、自分で腰を動かしながら、先輩のことを思い出し、声を上げながら激しくイキ果てた。
彼女は、身体を押し付けたまま、震えながら息を整え、自分の汗ばんだ身体を横に倒した。自分で繰り出した快感の波に押し流された後、まことは、自分がしたことに恥じらいを感じながら、眠りに落ちていった。
まことは先輩の体を思い浮かべながら、自分の中に深く挿入していくと、その快感に酔いしれていった。
「あぁ、先輩、気持ちいい…もっと、もっと…」
まことはスカートをたくし上げ、パンツの中に指を入れ、クリトリスを刺激しながら、激しく腰を動かした。
「んっ、んっ、あっ、あっ、あぁっ!」
快感が全身を包み込み、まことは身をよじらせながら絶頂に達した。
その後、まことはベッドに寝そべり、先輩のことを思いながら、満足そうに微笑んだ。彼女の中で燃え上がる欲望は、今後もますます募っていくことだろう。
まことは満足そうに微笑んだが、心の中では、まだ先輩に触れられたことがないことに寂しさを感じていた。彼女は自分自身に言い聞かせるように、次こそは先輩と本当の関係を持つために、もっと頑張らなければならないと思った。
しばらくして、まことは身体を洗い、部屋を片付けた。そして、先輩に会うための準備を始めた。
まずは、先輩に似た男性の人形を用意し、それを先輩と呼びながら、自分の欲望を満たす練習をすることにした。
「先輩、あなたのことが大好きです。どうか私を愛してください」
まことは男性の人形に話しかけながら、その身体を愛撫し、舌を絡ませた。
「あぁ、気持ちいい…先輩、こんなに私を求めてくれるのですね」
まことは身体を重ね、深くキスをしながら、自分を先輩に捧げた。
その後、まことは自信を持って、先輩との本当の関係を持つために、新たな決意を固めた。畳む
#小説
前回の小説とは違うパターンです。
下半身のみのオナニーの小説です。
ある日、木野まことは街を歩いていた。彼女はいつものようにセーラー戦士として悪を追いかけていたが、今日は何かが違っていた。
木野まことは自室に戻り、悪の存在を感じながらも、落ち着こうと試みた。しかし、心がざわつき、体が火照ってしまった。
そんな時、彼女は机の引き出しから小さな玩具を見つけた。彼女は恥ずかしさを感じつつも、先ほどの男性を思い出し、手に取った。
木野まことは、自分の部屋でベッドの上に寝そべり、先輩にそっくりな男性を想像しながら、彼との濃厚なエッチな妄想を膨らませていた。
彼女は恥ずかしいけれど、どうしても満たされたい気持ちが抑えきれず、自分の股間を玩具で刺激しながら、先輩似の男性が自分の体に触れる様子を思い浮かべた。
「ああ、先輩…もう我慢できないよ…もっと私を抱いて欲しいの…」
木野まことは、先輩にそっくりな男性に執拗に責められる想像をして、自分のパンツを脱ぎ捨て、恥ずかしい部分を露わにした。そして、彼女はスカートをたくし上げ、挿入しやすい体勢に身を置いた。
「ああん、気持ちいいよぉ…先輩の感じ方が分かる気がする…!」
彼女は激しい動きで玩具を挿入し、自分の股間を抉り取るような快感に酔いしれた。先輩似の男性に抱かれ、彼女は何度も高まり、喘ぎ声を漏らしながら絶頂を迎えた。
「ああ、もう…先輩…もう少しで…あああっ!」
彼女は身体を震わせ、息を荒くしながら、自分自身を満足させた。
「先輩、今度会ったら、こんなにエッチなことされたらどうしよう…。でも、やっぱり…してほしい…」
木野まことは、彼女が自分自身に欲望を抱いていることに少し戸惑いながらも、この興奮を忘れることができず、再びエッチな妄想に耽り始めた。
深く突き刺さる快感に、まことは自分でも驚くような悲鳴を上げた。先輩そっくりの男性の陰茎が、自分の中で激しく動いている。その上から、別の手がクリトリスを弄りながら、まことを更に高みに誘っていた。
「あああっ、もうイッちゃう…イクイクイクっ!」
まことは必死で声を押し殺したが、とうとう自分の身体を抑えることができず、甘美な絶頂が押し寄せた。全身が痙攣し、目の前が一瞬白くなった。
その後、まことは呆然と横たわっていた。こんなに激しい快感を味わったのは初めてだった。先輩そっくりの男性に身体を貪られ、何度も何度も絶頂を迎えた。気がつけば、彼女はもう深夜で、明日は学校があるというのに、眠りに落ちてしまっていた。
翌日、まことは学校に行くのが億劫だった。一晩中、先輩そっくりの男性と快楽に没頭してしまったからだ。しかし、彼女が教室に入ると、そこには驚きの光景が広がっていた。
「木野さん、良かった。ちょうど君に言いたいことがあったんだ」
先生がまことに近づいてきた。クラスメイトたちが謎のワクワクした気配で彼女を見ている。
「え、どうかしましたか?」
「君が帰った後、校門前に先輩が来たんだよ。待ってるって。何か伝えたかったらしい。ちょっと急いでくれと。何だったんだろうね」
「あ、あの……ありがとうございます」
まことは、心臓が止まるかと思うほど興奮していた。こんな嬉しいことがあるだろうか。先輩が自分を待っている。早速、まことは教室を出て、校門前に向かった。
校門前で、まことは先輩そっくりの男性と出会った。彼はまことに優しく微笑みかけた。
「あ、先輩。お呼びですか?」
「ああ、まこと君。実は
まことは、先輩そっくりの玩具を使って、激しく自分を責め立てた。挿入された玩具が彼女の中で激しく動き、膣内を突き上げるように蠢いていた。
「ああっ、先輩、こんなに激しくされたら、私、もうダメぇ…」
まことは、先輩にそっくりの玩具を膣内に突き立てたまま、恥ずかしい喘ぎ声を漏らし、身体を震わせた。彼女は、自分で操作する玩具に慣れていたため、自分自身で快感をコントロールしながら、一人Hに耽っていた。
しかし、やがてまことは、もう少し激しい刺激を求め始めた。彼女は、自分で腰を動かしながら、玩具を膣内に押し込んだり引き抜いたりして、さらに快感を高めようとした。
「もうダメ、もう我慢できないっ!」
まことは、自分で腰を振りながら、熱くなった股間に激しい快感を感じ始めた。彼女は、先輩そっくりの玩具を激しく突き上げながら、自分で乱暴に責め立て、身体を震わせた。
「先輩、私、先輩が欲しいのっ!」
まことは、自分で腰を動かしながら、先輩のことを思い出し、声を上げながら激しくイキ果てた。
彼女は、身体を押し付けたまま、震えながら息を整え、自分の汗ばんだ身体を横に倒した。自分で繰り出した快感の波に押し流された後、まことは、自分がしたことに恥じらいを感じながら、眠りに落ちていった。
まことは先輩の体を思い浮かべながら、自分の中に深く挿入していくと、その快感に酔いしれていった。
「あぁ、先輩、気持ちいい…もっと、もっと…」
まことはスカートをたくし上げ、パンツの中に指を入れ、クリトリスを刺激しながら、激しく腰を動かした。
「んっ、んっ、あっ、あっ、あぁっ!」
快感が全身を包み込み、まことは身をよじらせながら絶頂に達した。
その後、まことはベッドに寝そべり、先輩のことを思いながら、満足そうに微笑んだ。彼女の中で燃え上がる欲望は、今後もますます募っていくことだろう。
まことは満足そうに微笑んだが、心の中では、まだ先輩に触れられたことがないことに寂しさを感じていた。彼女は自分自身に言い聞かせるように、次こそは先輩と本当の関係を持つために、もっと頑張らなければならないと思った。
しばらくして、まことは身体を洗い、部屋を片付けた。そして、先輩に会うための準備を始めた。
まずは、先輩に似た男性の人形を用意し、それを先輩と呼びながら、自分の欲望を満たす練習をすることにした。
「先輩、あなたのことが大好きです。どうか私を愛してください」
まことは男性の人形に話しかけながら、その身体を愛撫し、舌を絡ませた。
「あぁ、気持ちいい…先輩、こんなに私を求めてくれるのですね」
まことは身体を重ね、深くキスをしながら、自分を先輩に捧げた。
その後、まことは自信を持って、先輩との本当の関係を持つために、新たな決意を固めた。畳む